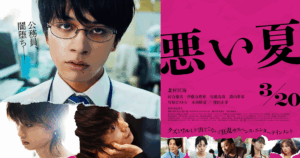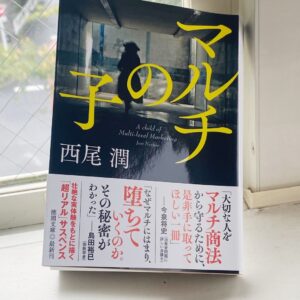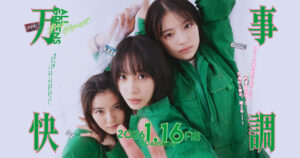【映画レビュー】辻村深月「この夏の星を見る」感想まとめ【haruka nakamuraが良い味を出す】

こんにちは。Nagiです。
当サイト(Nagi Rhythm)は現在1500記事以上投稿をしており、過去に様々な映画やドラマのレビュー記事をご紹介させていただきました。
本日は昨日から公開されている辻村深月さん作「この夏の星を見る」を映画館で見てきたのでレビューをまとめさせていただきます。
感想を一言でお伝えすると、これまでに観た1,000本以上の映画の中で、最も映像と音楽が美しい作品でした。
映像が美しい映画はたくさんあります。けれど、この作品の美しさは、ただ目で楽しむものではありません。
“音と光が感情に直接触れてくる”ような、不思議な体験がありました。
感動を押しつけてくるような場面があるわけでもないのに「星を見に行きたい」と心から思えた映画は、この作品が初めてです。それでも、見終わったあとには静かに胸が満たされていて、言葉にならない余韻がじわじわと広がっていきました。
本記事では、なぜこの映画がそこまで心に残ったのかを、映像、音楽、テーマ、そして自分自身の内面に照らしながら、レビューさせていただきます。
「この夏の星を見る」のあらすじ
物語の舞台は、2020年の日本。
新型コロナウイルスの影響で、学校生活や部活動が思うようにできなくなった高校生たちがいます。茨城県立の高校に所属する天文部の女子生徒・溪本亜紗(けいもと あさ)は、仲間と共に「オンラインスターキャッチコンテスト」を企画。
それは、離れた土地にいる天文部の仲間たちと、空を見上げながらつながろうとする試みでした。舞台はやがて、東京、長崎、五島列島へと広がっていきます。
星を観測し、写真に残し、オンラインで共有する――そんなひとつひとつの行為に、孤独な時代を乗り越えようとする若者たちのまっすぐな意志が宿っています。マスク越しの会話、リモートでの出会い、距離のある友情。
制限だらけの日々の中で、彼らは「見えない星」と「見えない誰か」を信じて、前に進もうとしていました。
音楽と映像が感情を動かす理由
この映画のいちばんの魅力は、映像と音楽が一体となって心を揺さぶる力にあります。
物語の中で泣けるような展開があるわけではありません。
それでも、haruka nakamuraの音楽が流れた瞬間、鼻の奥がツンとするような感覚が確かにありました。
もう1年くらい前なのに破壊力MAXです。
ルックバックの映画レビューについてはこちらをご覧ください。
これは理屈ではなく、音の重なりや静けさ、余白に近い旋律が感情の芯にふれるような感覚を呼び起こしていたのだと思います。
長崎県五島の景色の美しさがえぐい

↑のような景色がノンフィクションでずっと続きます。
ただの「きれいな星空」ではなく、目に映る光景はどれも、静かで、澄んでいて、どこか切ない。
特に印象に残ったのは、以下のようなシーンです。
-
息を呑むほどの圧巻の星空
-
2度と戻れない青春生活の一瞬
-
マスクをつけたまま交わす視線と沈黙の温度
どの場面を切り取っても、まるで写真集のように美しく、でもそこには確かに感情が宿っているようにも思えました。
コロナ禍の青春と“見えないつながり”
この映画が描いているのは、ただの青春ドラマではありません。
「何もできなかった時代に、それでも何かをしようとした若者たち」の物語です。見た人は全員わかるとおもいますが、「先生も生徒から1番学んでいる」ようにも思えました。
登場人物たちは、マスクをつけたまま、リモート越しに会話をして、望遠鏡を通して空を見上げます。
できることは限られている中で、彼らは手を伸ばし、誰かとつながろうとしていました。
10代の若者からしか得られないインプットがある
この感覚には、観ている側も心を動かされます。
「できない理由」を並べて立ち止まるのではなく、制限のなかでも何かを探し続けようとする姿勢は、それ自体がまぶしく見えました。
特に印象的だったのは、彼らが「つながっている」と実感する瞬間の描き方です。
-
空という同じものを見ていること
-
画面越しでも伝わるまなざし
-
一緒に空を見上げた“記憶”の共有
星空というモチーフは、実際には誰のものでもなく、手に取ることもできません。
それでも、「同じ空を見ている」と思うだけで、人と人がちゃんとつながっている気がしてくる。
この映画はその感覚を、押しつけではなく丁寧に描いていたように思います。
SNSと空、自分自身を見つめ直す視点
この映画を観たあと、ふと自分の生活を見つめ直したくなりました。
理由はとてもシンプルです。何も加工していない“空”のほうが、美しかったからです。
これは映画を観終わった直後の、まぎれもない実感でした。
- 「人に見せる前提」で行動していたこと。
- 「“いいね”がつくかどうか」で価値を測っていたこと。
そのすべてが、一度スクリーンの前で立ち止まるきっかけをくれました。
この作品に登場する高校生たちは、スマホを使いながらも、画面の向こうではなく“空そのもの”を見ていました。誰かの承認や評価よりも、「見えないけれど確かにある何か」を信じて行動していたのが印象的です。
それは、いまを生きる私たちにとっても、本当は大切な感覚だったはずですなので「ハッ」とさせられました。
映画を観終わったあと、スマホをいじるよりも、何も投稿しなくてもいいからただ空を見上げたくなったし、それだけで、この映画はたしかな価値を持っていたと感じました。
観終わったあとの余韻と行動の変化
映画を観終えたあと、真っ先に思ったのは、「地元に帰って、星を見に行きたい」という感情でした。
映画を観て何かを考えることはよくありますが、「何かをしたくなる」「実際に行動したくなる」ことは、そう多くありません。
- 地元に帰ったら星を見に行きたい
- それに長崎県の五島にも1泊2日でいいので旅に出かけたくなった。
この気持ちは、ただの感傷ではなく、心が動いたことの証拠のように感じます。
作中で描かれていたのは、「星を見る」というシンプルな行為です。たった2時間程度の映画が、これほどまでに人の心を動かすということに、自分でも驚きました。
おなじコロナ映画「フロントライン」とセットで見ると面白い
個人的に全く違うジャンルであれど、2020年3月時点のダイヤモンドプリンセス号をフォーカスした「フロントライン」とセットで見ると、より一層エモさを感じて良いと思いました。
レビュー記事についてはこちらをご覧ください。
どちらも同じ時代を、まったく違う角度から描いています。
その両方を見比べてみると、2020年という特異な時間が、立体的に浮かび上がってくるように感じました。
この映画の魅力は、観ている間の感動だけでなく、観終わったあとに自分がどう動くか、何を感じるかにあるのだと思います。
まとめ

『この夏の星を見る』は、派手な展開やわかりやすい感動を用意している映画ではありません。
けれど、映像と音楽、そして登場人物たちの静かなまなざしが、確かに感情に届く映画でした。とにかくharuka nakamuraとヨルシカコラボが最高すぎました。
僕自身、観終わったあとに感じたのは「心の深いところに水面の波紋のような感情が広がっている」という静かな実感だったとおもいます。
「泣ける」「感動した」といったシーンは1mmもないのに、心がやたら惹きつけられるそんな作品です。
メディアをユーザーと共に作る。
Nagi Rhythmは、SEOを完全に度外視した読者と交流ができるウェブメディアを目指しています。
この記事への感想、または個人的なご相談など、どんな「熱」のあるお便りも歓迎します。